ゲーム会社はしばしば嘘をつきます。
実装すると言っていた機能がいつまで経っても実装されなかったり、サービス終了しないと明言していたのに突然終了されたり等、嘘をつかれた経験がある人は多いのではないでしょうか?
もちろんゲーム会社も好き好んで嘘をついている訳ではありません。少なくとも僕が知る限りは「嘘をつくつもりはなかったが、紆余曲折を経て嘘になってしまった」みたいなケースがほとんどです。
そんなわけで今回は、よくあるゲーム会社の嘘とその内情を実例を交えて紹介しようと思います。
「品質向上のため延期します」→品質向上しない
ゲームのリリース延期が発表される時、結構な確率で出現するのが「品質向上のため、延期を決断しました」といった類のフレーズです。
しかし実際にリリースされたゲームをプレイしてみると、「何が良くなったのか全然わからない」と感じたことがある人は多いのではないでしょうか?
※もちろん中には「めちゃくちゃクオリティあがってる!」と驚くようなゲームもあります
実はこれ、厳密に言うと嘘ではないケースが多いです。
問題なのは、ユーザー側の期待する「品質向上」と、開発側の言っている「品質向上」が大きくずれてしまうことになります。
ユーザーの期待する「品質向上」とは全然別の「品質向上」をされた結果として、ユーザーが「嘘をつかれた!」と感じてしまうのです。
ユーザー側が期待する「品質向上」は、「グラフィックが大幅に良くなった」「便利機能が増えた」といったような、目に見えてわかる改善です。
しかもそれは、「すでに完成に近いゲームにさらに追加で改善されたもの」を期待しがちです。
一方開発側にとっての「品質向上」は、「コードの可読性が著しく低かったので修正して保守性を上げた」「ゲームエンジンのバージョンがサポート切れ間近だったのでバージョンを更新した」といったような、必ずしもゲームプレイに影響があるとは限らないことも含まれます。
さらには、「ゲームの機能の多くが未実装」「ロードが長すぎてとてもプレイに耐えうるレベルではない」といった、低品質なものをまともな状態にするレベルの改善も「品質向上」として扱います。
要するに、ユーザー側はゲーム体験がより良くなることを「品質向上」と認識していて、開発側はゲーム体験に関係ない改善や低品質なゲーム体験を少しでもマシにする改善も「品質向上」と認識している訳です。
ユーザーはより良いゲーム体験を期待していたのに、目立った変化がなければ「嘘をつかれた!」と感じるのも仕方ありません。
ユーザー側と開発側の「品質向上」の認識が一致していても、ユーザーの期待する水準に到達できないケースもあったりします。
僕が昔関わっていた、アクション性の高いブラウザゲームの開発では、ベータテストの評価が散々なものでした。
原因は、ブラウザ環境特有のカクつきや読み込みの不安定さでした。
そこで開発チームは品質向上のためのリリース延期を発表しました。
ユーザーは正式リリースまでにアプリ化されて快適になることを期待しましたが、開発チームはブラウザの限界まで最適化する方針を取りました。
最終的に多少の改善は見られたものの、ユーザーの期待には及ばず、そのゲームは日の目を見ることなく開発中止となってしまいました。
「開発は順調です」→不具合が出たり延期したりする
「開発は順調に進んでおります」というフレーズは、ゲームの新作発表時や定期レポート、公式放送などでよく耳にします。
そしてこのフレーズの数週間後に、「発売延期のお知らせ」や「深刻な不具合が見つかりました」といった告知が出ることは、もはや珍しくありません。
この「順調」という言葉、実はかなり曖昧です。
一般的な感覚では「もうすぐ完成しそう」「スケジュール通り進んでいる」といった印象を受けますが、開発側では「致命的なブロッカーがない」「少し遅延しているが取り戻せるレベル」といったかなり控えめな意味で使われることも珍しくありません。
「正直に進捗を報告してしまえば良いのでは?」と思われるかもしれませんが、それができない事情があるケースも多々あります。
例えば、自社あるいは協業している他社の株価への影響を考慮して経営層から圧がかかっていたり、ユーザーの不安や不信感を和らげるためといった理由で、「順調です」以外の発言が許されない状況だったりします。
もちろん進捗遅れの原因が解消できなければ、結局順調でなかったことがバレてしまうのでより大きなダメージを受けてしまいます。
それでもついつい「なんとか軌道修正して順調路線に戻れる」可能性にかけたくなってしまうのでしょう…(笑)
また、開発側の見積もりが甘いケースも多々あります。
例えば、開発期間の前半は実装が容易なタスクが集中していて、逆に開発期間の後半は実装が難しいタスクが集中しているゲームがあったとします。
開発期間の前半では、実装が容易なタスクしかないので当然開発は順調に進みます。
ところが開発期間の後半では、実装が難しいタスクが盛りだくさんなためどんどん遅延が発生していきます。
そして「順調順調と言っていたのに全然完成しないゲーム」の出来上がりです。
僕がよく経験するのは「すでに外部に〇日にリリースと発表してしまっているから、絶対に実装を間に合わせなければいけない」という状況です。
今まで10個以上のゲームのプロジェクトに関わっていますが、どのプロジェクトでも1度はそんな状況になったことがあります(笑)
「バグは近日中に修正します」→調査も終わってない
「現在確認されている不具合については、近日中に修正を予定しております」
多くのゲームで見かけるコメントです。
大抵のバグはちゃんと修正されるのですが、中にはいつまで経っても修正される気配が欠片も見られないバグもあります。
再現性のあるバグであれば、どれだけ複雑なバグだったとしても少しずつ調査は進むので、いつかは原因が特定でき修正対応もできます。
しかし再現性がなくたまにしか報告があがらないバグ等は、いつまで経っても調査がなかなか進みません。
そうなると当然ながら「○日までに完了予定」なんて見積もりができないので、「近日中」というふわっとした表現にせざるを得ないです。
(逆に言うと、「〇日のアップデートで修正予定です」みたいに期日を定めているケースでは、修正の見込みが立っている可能性が高い訳です)
ただし、いくら調査難易度が高いバグでも「ユーザーのデータに不整合が生じる」「ゲームが進行できなくなる」といったような緊急性の高いバグであればいつまでも放置する訳にもいきません。
そんな時はバグそのものを修正するのではなく、「ユーザーのデータ不整合を修正するバッチを定期的に実行する」「進行が止まる箇所を try-catch で囲んで落ちないようにする」といった力業に出ることもあります。
ゲーム開発の現場でよくあるケースですと、1ヶ月~数か月に1度くらいの低頻度で問い合わせのくる調査難易度が高いバグに対して「現在調査中です。今しばらくお待ちください。」的な回答をすることがよくあります。
ユーザーへの影響が小さい等の緊急性が低いものであれば、ユーザーへの申し訳なさは感じつつも短期間で修正するのはおとなしく諦めます。
そして、あやしい箇所にログを仕込んで調査に必要な情報が溜まるまで待ちます。
無事調査が終われば修正完了後、ユーザーに謝罪とともに不具合解消の連絡をします。
長い付き合いだったバグが解消すると、普段のバグ修正とはまた違った謎の達成感があります(笑)
「再発防止に努めます」→数か月後にまたやらかす
炎上や重大な不具合が発生した時、運営からの謝罪文には「再発防止に努めます」という一文が出てくることが多いです。
謝罪文としては妥当ですし、実際その通り努力している運営もちゃんといます。
しかし、数か月後に似たような問題が再び発生し「努めてないじゃん!」とツッコミが入りそうなパターンもあります。
いくつか原因は考えられますが、多くは以下のパターンのいずれかになります。
- 再発防止策の内容が甘かった
- 再発防止策が形骸化してしまった
- そもそも再発防止策を作ってなかった(論外)
1.は「Aの現象は対策できてるけど、Bの現象は対策できてない」「対策の内容が複雑すぎて現実的ではない」といった感じです。
運営が経験不足だったり、そもそも問題が複雑だったりするとこのパターンになりがちです。
再発防止策を更新するたびに徐々に改善されていくので、いずれはきちんとした再発防止策が出来上がるはずです。
2.は「再発防止策の存在を忘れ去られてしまった」「再発防止策のメンテナンスがされずに最新のゲーム仕様では使い物にならない」といった感じです。
再発防止策の対応が属人化していたり、再発防止策の存在を知っていたのが一部の人だけだったりするとこのパターンが起こりがちです。
再発防止策を作成した後に、「チームへの周知の徹底」「ドキュメントを分かりやすい場所に置く」といったことを忘れずに行うようにしましょう。
3.は論外です。
そんなことをしている運営であれば先行き不安です。
あなたが発言力を持っているのであれば、きちんと運営方針の軌道修正をしてあげてください。
ゲーム開発現場における再発防止策は、基本的にはテストケースの追加です。
重大な不具合に対する再発防止策は「その不具合が発生しうるケースでの動作確認を行う」というテストケースを追加する形になることが多いです。
したがって、長く運営していて様々な問題に出くわしてきたゲームは多くのテストケースが追加されています(笑)
「期間限定の~」→しばらくしたら再登場
「期間限定イベント」「期間限定報酬」等はゲームではよく出てくる宣伝文句です。
かくいう僕も「期間限定」という言葉には弱く、常設のものであればスルーしているものも「期間限定」であればついつい遊んだり課金したりしてしまいます(笑)
実際に、僕が関わってきたゲームも魅力的な「期間限定」のイベントや商品が出ている時はかなりの売上をあげていました。
そして「期間限定」だから奮発して課金したのにその後しれっと再登場されてしまってモヤモヤするのもあるあるだと思います。
「期間限定」という言葉はそれほど強力な宣伝文句ですから、ゲームの運営もできるだけ積極的に使おうとしてきます。
もちろんその宣伝文句が出た時点では「期間限定」というのは嘘ではないかもしれませんが、様々な理由で後々再登場させてしまうことはよくあります。
僕が見てきた中でよくあるパターンが、運営側が売上を出したくて再登場させるパターンです。
ソーシャルゲームをはじめとした運営型のゲームでは、どうしても売上を出したいタイミングというものがあります。
ゲームの存続が危うくなってきていたり、そもそも会社の経営が危なかったりすると、なりふり構わず売上を出さざるを得なくなります。
そして売上を出す手段の1つとして、過去に好評だった「期間限定」の再登場を行う場合があります。
もう一つよくあるパターンとして、ユーザーからの要望が無視できなくて再登場させるパターンもあります。
主に「期間限定」の後に新規参入したユーザーや、諸事情で期間中にゲームを遊べなかったユーザーから、「期間限定」の再登場の要望が届きます。
特に、その「期間限定」の恩恵を受けたかどうかでゲーム内資産に大きな開きが出れば出るほど、要望は強くなります。たまたま遊べなかった期間があっただけで、他のユーザーと大きな差をつけられてしまうと不公平感がありますからね。
最終的に運営側がその要望を飲み、「期間限定」の再登場となることもよくあります。
僕が過去に参画していたとあるゲームは、月の売上目標に全然届いていない時がありました。
そこで当時のプロデューサーが、「期間限定」で出していた強力なキャラを再登場させることにしました。
もともとそのキャラは強力すぎたので再登場させる予定はなく、ユーザーからも度々要望はありましたが断固として再登場させていませんでした。
そんな状況での再登場だったので、諦めていたユーザーの課金欲の爆発はすさまじく、あっという間に月の売上目標を大幅に超える成果を出しました。
「今後のロードマップ公開!」→未達成項目だらけ
長期運営を見据えたゲームでは、今後のロードマップを公開することがあります。ちなみにここでいう「ロードマップ」は機能の実装スケジュールのことを指します。
ロードマップの公開はユーザーの期待を煽る目的が主なので、当然ワクワクするような内容が多いです。
ですが「期待に胸を膨らませて待っていたものの、いつまで経っても新機能がリリースされない…」「いつの間にかロードマップから○○の機能がなくなってる…」なんて経験をした人もいるでしょう。
これに関しては厳密には嘘とは言えません。
ロードマップはあくまで予定だからです。
予定通りいくこともあれば、運営側の諸事情で予定通りいかないこともあります。
とはいえ、ユーザーからすればそんな事情は知ったこっちゃないかもしれませんけどね(笑)
今までの経験上、ロードマップが変わるのは主に以下の要因です。
- 単純に開発が間に合わなかった
- 明らかに無茶なスケジュールなのに、協業他社の事情でゴリ押されてしまった
- とある機能に対するユーザーの需要の低さに気づき、優先度がかなり低くなった結果放置された
- ゲームの売上が芳しくなく、機能実装の予算を確保できなかった
- プロデューサーが変わり、ゲームの運営方針が大幅に変わった
昔関わっていたゲームでは、リリース当初から実装を予定している機能がありました。もちろんユーザーにも公表済みです。
しかし、バグ対応やもっと優先度の高いゲームのユーザー数や売上確保のためのテコ入れの対応に追われ、結局その機能はいつまで経っても「ComingSoon」のままでした。
「サービス終了しません」→数か月後にサービス終了
個人的には、数あるゲーム業界の嘘の中でも一番つらいやつです。
主にそこまで賑わっていないゲームの運営が、ユーザーの不安を払しょくするために「現時点でサービス終了の予定はございません」と発することがあります。
しかし、ゲームの運営はユーザー数や売上、会社の経営方針といった様々な問題をクリアしないと継続できません。
そしてそれら諸問題をクリアできるゲームは意外と少なく、結果的にサービス終了となり悲しい嘘が出来上がってしまいます。
大抵は売上が確保できずにサービス終了となるパターンですが、「主要人物が急に抜ける」「クラッキング等でサーバーのデータが消失する」等の思いもよらぬトラブルに見舞われてサービス終了してしまうこともあったりします。
幸い僕はそんなトラブルに出くわしたことはありませんが、「本当にあった怖い話」的なノリで同業の人からトラブル事例を聞くことはよくあります。
実はこの嘘、ユーザーだけじゃなく、運営をしている開発メンバーですら騙されることがあります。
「内部の事情を知ってるのにどう騙されるんだよ!」というツッコミはごもっともですが、僕も過去に何度か騙されたことがあります。
そんな開発メンバーも騙される嘘をいくつか紹介します。
「売上○○円以上を達成出来たらサービス終了はさせない」→サービス終了
当時、とあるIPもののゲームの運営に関わっていました。(IPもののゲームとは、簡単に言うと漫画やアニメといった原作があるゲームのことです)
詳しい説明は長くなるので省きますが、IPもののゲームというのはIPの版元にも売上の一部を渡す場合が多く、損益分岐点が高い傾向にあります。
そのゲームは売上自体はそこそこ出ていたのですが、会社に残る利益としては微妙なラインにあり、サービス終了が危ぶまれている状況でした。
そこでサービス終了を回避すべくプロデューサーがマネージャーと交渉し、「売上○○円以上を達成出来たらサービス終了はさせない」という言質を取りました。
この時提示された売上の額は当時の月の平均売上の倍以上ありました。
おそらくマネージャーも無茶な条件を提示して諦めさせる意図もあったのだと思います。
ところが予想に反して、大人気のキャラを中心にしたガチャ戦略がヒットし、なんと提示された売上額を達成してしまいます。
開発メンバーは「これでサービス終了を回避できる!」と喜んだものですが、結果としては状況は変わらないままサービス終了となってしまいました。
もしかしたら「マネージャーも手を尽くしたものの力及ばず…」という事情があったのかもしれませんが、僕を含めた開発メンバーの落胆ぶりはすごかったです。
「〇月までは絶対サービス終了させない」→〇月より前にサービス終了
当時、売上が全然あがっていないゲームに関わっていました。
開発メンバーは数十人といたものの、売上は月数万円と規模に対して少なすぎるものでした。
とんでもない赤字ゲームだったと思います。
そんな赤字ゲームにも関わらず、「〇月までは絶対サービス終了させない」と経営層からお墨付きをもらっていました。(〇月は半年先くらいのやや猶予がある感じです)
ゲームの内容自体は少し変わっていてチャレンジングな内容だったので、経営層も「もう少し挑戦させてみよう」と思っていたのでしょう。
もちろんそんな経営層の意図をくみ取った開発メンバーは、「〇月までに大規模アップデートを行い結果を出す」ことを目標に頑張っていました。
ところが、「大規模アップデートの企画が定まりいざ開発が本格始動!」というタイミングで無情にも経営層からサービス終了が言い渡されました。
おそらくは「経営方針が変わり、赤字削減に舵を切った」みたいな感じでしょう。
数十人いたメンバーは別チームに異動あるいは契約終了となりました。
僕は開発の本格始動の直前に参画していたため、ものすごい肩透かし感を食らいました(笑)
まとめ
ここまで、ゲーム会社がよく使う「嘘」とその背景事情について解説してきました。
振り返ってみると、どれも実は完全な嘘ではないケースが多いです。
「ユーザー側の認識と運営側の認識にずれがあって、結果として嘘っぽくなってしまった」「最初は嘘のつもりはなかったが、後々発生した諸事情により嘘になってしまった」なんてパターンが多いです。
少し言い訳っぽく聞こえるかもしれませんが、「嘘をつかれた!」と感じても多少は上記の事情を汲んでいただけるとゲームを運営する側としてはありがたかったりします。
ユーザーとしての心構えとしては「嘘かもしれないけど、ちょっとは期待しておこう」くらいの感じがちょうど良いかと思います。
完全に疑ってかかるのも寂しいですし、かといって完全に信じてしまうと嘘だった時のダメージが半端ないですからね(笑)
あなたなりの楽しみ方をしていただければ幸いです。
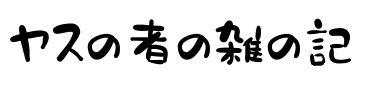


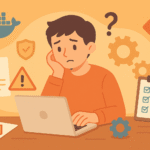
コメント